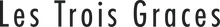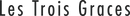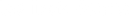連載:わたしたちのサステナライフ #6
身近な人のエシカルな習慣や最近使っているエコフレンドリーなアイテムって?
そんな好奇心から、レトロワグラースのメンバーでスタートしたリレーコラム。

第6回の担当はレトロワスタッフぐるっと回って青木です。みなさん、第1回目のスタッフコラムはご覧になりましたか?
第1回目では、自身のサステナ手料理を紹介した彼女が今回紹介するものとは?
日本の受け継がれる伝統を体験してきたレポートをお届けします。
突然ですが
皆様は柿渋ってどんなイメージですか?
漠然と柿からとった渋液で、柿含まれるタンニンより「防腐」作用があるくらいにしか予備知識がなかった私ですが。
今回は、日本の三大柿渋産地の1つとして今もその伝統が残る岐阜県美濃地方にある池田町を訪ねました。
そこで、柿渋染めが糸や布に色をつけるための染料としてだけでなく、生活の知恵として古くから日本の文化に馴染みがあったものということを伺ってきました。
この地方の柿渋に使われる下記の種類は、田村柿と伊自良柿。
どちらも美濃地方固有の品種で最も柿渋染めに適した品種だそうです。

柿渋に使う柿は渋柿で、8月のお盆前後、まだ実が青い状態で収穫します。
収穫された青柿は粉砕、圧搾されて絞り出した果汁を発酵させるのですが柿渋液として使えるまでには少なくとも3年はかかるそうです。
時間をかけて熟成した液は撥水・防水性に優れていて、昔は蓑や雨傘のコーティングとして使われていたとのことです。
以前この地域では、それぞれの家の玄関に柿渋を保存する甕があり、畑へ出かける前に雨具に柿渋液をかけ農作業へ出掛けたそうです。

また、漁をする際に使用する網に柿渋を施すことで、水に濡れた網が重くなるのを防ぐ役割もあったとのこと。
家屋の木材や漆喰にも使用でき、人にも環境にも優しい自然の塗料でもあるのです。
環境の移り変わりに応じて、呼吸するように変化する柿渋染め。湿度や温度、その他の環境の条件によって染めた後も色が変わっていくとのこと。
明るい気分の日もあれば、そうでない日もある。
まるで私たちと同じように生きているようで、なんだか親近感が湧きました。

色が薄くなってきたらまた染め直すこともできますし。鉄や石灰など自然界にも存在する色々な表情を見せてくれる柿渋染めは、長く大切に使うことで変化も楽しめそうですね。
山に囲まれた地域であるとともに木曽三川を有するこの地域ならではの自然環境。
ここで生活の知恵として受け継がれてきた柿渋の文化ですが、後継者不足や関わる人の人手不足により現存する柿渋の生産農家さんは2軒にまで減ってしまったそうです。

便利なものが手軽に手に入る時代ではありますが、本来の人の生活や自然環境に近い暮らしの知恵は大切に受け継いでいきたい。柿渋で染められた手ぬぐいを眺めながら改めて実感しました。
そんな、伝統的な技法:柿渋で染めた手ぬぐいはこちら。
レトロワグラースデパートメントオリジナル商品としてご用意させていただきました。
Edit & interview: aoki & muu
この記事に関連するアイテム
柿渋クロス
関連記事
レトロワスタッフがお届けする 連載:わたしたちのサステナライフ